流通小売業に強い

私たちが得意とする業界は流通小売業です
私たちの代表は流通小売業出身です。学生バイトを含めると、コンビニ、食品スーパー、総合スーパー、卸売会社、物流センターで働いてきたので、流通チャネルのあらゆる現場を熟知しています。日商1級販売士でもあり、リテールマーケティングの専門知識も確かです。
流通小売業における人事マネジメントの特徴
小売業は労働集約型産業であり、人事マネジメントの巧拙が業績に直結します。一方で少子高齢化や就労観の多様化によって、小売業特有の収益構造や雇用慣行に起因する人事管理上の問題が顕在化しつつあり、多くのリテーラーでは人事マネジメントの難度が増しています。
全産業における最大勢力だがほとんどが零細事業者
令和3年経済センサスによると、卸小売業で働く従業者数は国内の全ての産業において最多だが、1事業所あたりの従事者数は10人に満たない。つまり就業規則の作成義務や衛生推進者の選任義務などが適用されない事業者が多く、労務コンプライアンスに準拠した適正な人事管理が行われていない可能性がある。
従業者1人あたりの付加価値額(収益力)が小さい
業界全体では付加価値額が大きいが、従業者1人あたり付加価値額に換算すると国内産業の中では下位グループに入るため、人材投資に充当する原資が乏しくなりがち。雇用条件の低さゆえに人材採用において他の産業に競り負けたり、充分な社員教育ができないことからサービスの質が低下したりする恐れがある。
初任給は悪くないがその後の昇給は期待できない
月の平均的な賃金は、若年層ではどの産業も似たりよったりだが、中高齢層になるにつれて産業ごとの収益力の違いが、賃金格差として如実に現れてくる。現在は子ども子育て推進のための様々な政策が打ち出されている一方で、子ども子育て世代の賃金水準が低ければ、出産育児のモチベーションは上がらない。
従業者は男女半々だが女性管理職は少ない
卸小売業における女性従業者の割合はほぼ半分で全産業中6位。しかし女性管理職はわずか14%と女性人材の登用が進んでいない。これは女性従業者の多くがパートタイマーなどの非正規雇用であることが影響しているが、これらの層は主婦(消費者)でもあるため、マーチャンダイジングに活用しない手はない。
帰れない・休めない→悪しき慣習から脱却せよ
当社代表が販売の最前線で働いていた時から、流通小売業は帰れない・休めない業種の典型だったが、年次有給休暇の取得状況を見る限り、その悪しき慣習は未だ改善されていない。経営者は従業員満足あっての顧客満足ということをよく認識されたい。理由は不幸な人が他人の幸福を追求したりしないからだ。
人事生産性の向上こそ小売業経営の生命線

多くのリテーラーは利益率が低く、付加価値額をコントロールしづらい一方で、昨今の賃上げ圧力との板挟みとなっていますが、その解決策のひとつが人時生産性の向上です。
人時生産性を改善することで総額人件費を抑制しつつ、個々の人材への投資を高めてゆけるかどうかが、これからのリテール経営の生命線となってゆくでしょう。
私たちの人事コンサルティングの強み
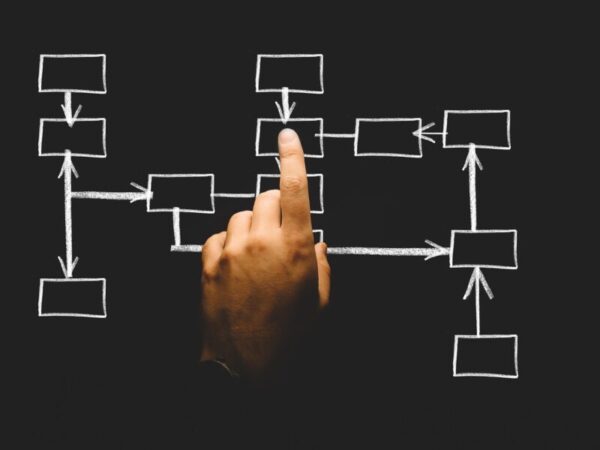
人時生産性の向上にはLSP(Labor Scheduling Program)の確立が不可欠です。LSPの確立には現状の業務を因数分解し、労働法令や社会保険制度との整合性をとりつつ、新たな職務要件定義とワークフローを整備して、作業のムリ・ムダ・ムラを排除してゆく必要があります。
そして的確なインタビューとファシリテーションを通じ、実効性あるLSP構築を支援できるのは、店舗オペレーションを知り尽くした当社代表ならではの強みです。
RWC合同会社/RWC社労士事務所のサービスを詳しく知りたい

🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。