はじめに
昨今はカスハラが社会問題化しており、特にパート・アルバイト比率の高いスーパー業界では、立場の弱い非正規雇用者を狙ったカスハラ行為が貴重な人材の離職を招いたり、風評被害により人材採用が困難になるなど、すでに看過できない経営リスクとなっています。
そこでこれから6回にわたり、かつて大手スーパーの販売課長としてカスハラ行為に対処した経験を有する当事務所代表が、人事のプロ(人事部出身の社会保険労務士)と元流通マン(日商1級販売士)の知見と経験をもとに、スーパー業界に”効く”カスハラ対策を提案します。
カスタマーハラスメントの定義と類型



カスハラはどのような行為をいうか?
厚労省「業種別カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル スーパーマーケット業編」は、カスハラを「顧客等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、実現手段・態様が社会通念上不相当なものであり、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。
度の過ぎたカスハラ(殴る、蹴る、小突く、備品を壊す等)は立派な犯罪行為であり、ハラスメントではなく傷害罪や暴行罪、器物損壊罪などに該当します。もはや警察に通報すべき事案ですが、スーパー業界では管理職の不知による対応遅れから被害が大きくなりがちです。
カスハラの典型的な3つのパターン
厚労省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルスーパーマーケット業編によると、カスハラの典型的な類型は次の3つであるとしています。なお同マニュアルには具体的なカスハラの事例とカスハラに該当するかどうかの判断基準なども明記されています。
- クレームの内容が妥当性を欠く
- 提供する商品やサービスに瑕疵や過失がない
- クレームの内容と商品やサービスが関係ない
- クレームの要求が不合理・不相当
- 過大な商品交換の要求
- 支払い義務の無い金銭補償の要求
- 過大な謝罪の要求
- クレームの手段や言い方が不相当
- 身体的攻撃(暴力、傷害)
- 精神的攻撃(脅迫、暴言、侮辱)
- 威圧的言動(怒声、土下座の要求)
- 拘束的行動(不退去、つきまとい)
- 個人的攻撃(従業員へのストーカー行為)
- 誹謗中傷の拡散(SNSによる名誉毀損)

カスハラ行為を放置するとどうなるか?

スーパーマーケット事業者が、自社で発生したカスハラ行為を放置すると、人事管理上のデメリットと営業活動上のデメリットという、二つの重大なリスクが発生します。
人事管理上のデメリット
安全配慮義務違反による損害賠償リスク
労働契約法により、使用者は労働者が安全で衛生的に働ける労働環境を提供する義務を負っています。使用者がカスハラ行為を放置すると安全配慮義務違反に問われ、労働者がなんらかの経済的損失を被った場合には、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。
カスハラ起因の精神疾患による労災多発
令和5年9月1日の厚労省通達により、精神障害の労災認定基準にカスハラ起因の精神疾患が追加されました。これによりカスハラによる労災認定が増えると予想されます。労災事故が多いと監督官庁から特別改善指導を受けたり、労災保険料がアップすることもあります。
ブラック企業に若い人材は寄り付かない
令和8年10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業者にはカスハラ防止措置を講じる法的義務が生じます。防止措置を講じようとしない場合は企業名が公表され、世間からブラック企業の烙印を押されると、新卒者やパート・アルバイトの採用が困難になります。
営業活動上のデメリット
熟練スタッフの離職がカスハラを招く
仕入価格や人件費の高騰により、利益率の高い生鮮部門や惣菜部門を強化するスーパーが増えています。これらは高度な加工技術と厳格な鮮度管理、豊富な商品知識が必須ですが、カスハラで熟練スタッフが離職すると、販売活動の質が低下してしまいカスハラを誘発します。
カスハラ被害者が増えると客離れする
スーパーマーケットはパート比率が高いですが、就労の動機が多様なので、カスハラ被害に遭うとすぐ離職してしまいます。これら非正規雇用者の多くは地域の生活者であり消費者でもあるため、勤務先のカスハラ体験がトラウマになることで客離れが起こることもあります。
負のスパイラルが売り場を崩壊させる
カスハラ行為に有効な対策を講じることができないと、離職者や休職者が増加し、残された従業員の業務負担とストレスが増大します。仕事に余裕がなくなると、商品管理や接遇応対の質が低下してクレームが増え、さらに従業員の離職や休職を招く負のスパイラルに陥ります。
カスハラ対策における重要なポイント
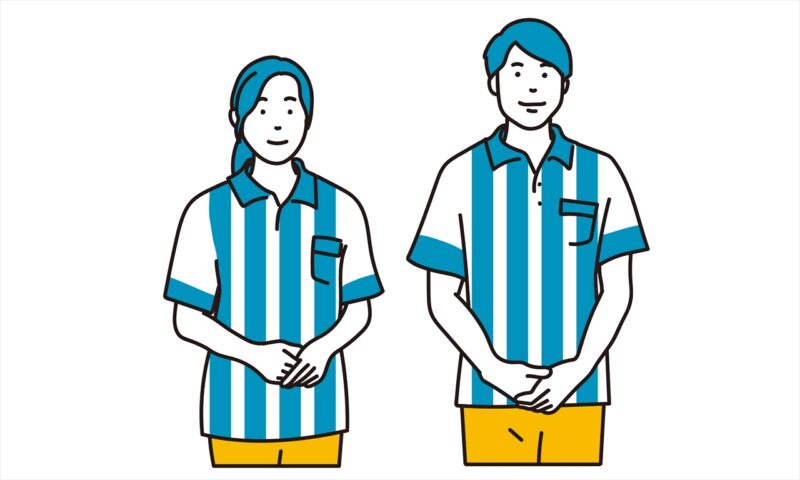
カスハラは接遇スキルの問題ではない
当事務所の代表がスーパー業界で働いていた頃は、カスハラという言葉はありませんでした。カスハラ行為と思しき行為は日常茶飯事でしたが、当時はクセのあるお客さんにうまく対処できるか否かは販売員の接遇スキルの問題であり、うまく対処して一人前という風潮でした。
しかし昨今の人材不足と人権意識の高まりにより、多くのステークホルダーがカスハラに対する企業の取り組みを厳しく評価するようになっています。カスハラは経営リスクであり、企業として取り組むべき課題であると認識しないと、事業継続すら難しい時代になったのです。
お客様ファーストとカスハラは別モノ
某演歌歌手の「お客様は神様です!」という言葉は、以前からカスハラ行為者の常套句として知られていますが、スーパーマーケット側が「お客様第一主義」をことさらに掲げてアピールしていることも、カスハラ行為を助長しているという意見があります。
マーケティングのセオリーは自社にふさわしい相手に対し、自社の得意なやり方で商品やサービスを提供することで、末永く良好な関係を築くことです。従業員を傷つけ、事業活動にリスクしかもたらさないような輩を、顧客として扱うこと自体が間違っているのです。
販売業は地域の生活インフラ産業である
令和7年4月1日に全国の自治体に先駆けて北海道でカスハラ防止条例が施行されました。この条例の要旨は概ね次のとおりです。
- 北海道民の便利で快適な日常生活は、流通業者などのエッセンシャルワーカーに支えられて成り立っており、道民はそのことをきちんと自覚せよ。
- 労働力不足が顕在化している北海道において、カスハラにより貴重なエッセンシャルワーカーを喪失することは、地域の損失であり許されない行為だ。
- ゆえに道民はカスハラ行為をするな。事業者はカスハラ防止のための具体的措置を講じて自社の従業員を守れ。
大手スーパーがこぞって社会貢献活動に取り組んでいるのは、自社のイメージを向上し、消費者からの支持を得ることを期待しているからです。従業員をカスハラから守り、地域の生活インフラを支え続けることも、立派な社会貢献活動であると考えるべきです。
まとめ
スーパー事業者の危機意識が足りない?
厚生労働省の調査によると、過去3年間に従業員からカスハラ相談を受けたスーパーマーケット事業者は76.2%でした。深刻なのは「カスハラが増加している」と回答した企業が42.9%に上る一方で、「しっかり対応できている」と答えた企業はわずか5.9%という現実です。
労働集約型産業であり、接客サービス業でもあるスーパーマーケット業において、良質な人材の確保と定着は経営の生命線であり、虎の子の熟練スタッフをカスハラで失っていては本末転倒です。人材が枯渇して打ち手が無くなってしまう間に、早急な対策が必要なのです。
スーパーのカスハラ対策は専門家に依頼
企業がカスハラ対策を怠り、明確な姿勢を示さなければ、人手不足が進む現在の雇用情勢において労働者から選ばれない企業となり、新規採用の減少や既存従業員の離職率増加を招きます。結果として事業存続すら危ぶまれる事態に陥る可能性があります。
一方で、適切なカスハラ対策を実施することにより、従業員に安心感を与え、満足度を向上させることができます。これは従業員のみならず、店舗を利用する他の顧客の安心感にもつながり、すべての関係者にとってプラスの効果(三方よし)をもたらします。
当事務所の代表は人事部出身の社会保険労務士で、前述のとおり大手スーパーの販売課長として数多のカスハラ事案に対処してきました。「人事のプロ」×「カスハラ経験者」の強みは業界で唯一無二であり、クライアントにとって満足のゆく成果をもたらすことができます。

流通業界に精通した社労士による実効性あるカスハラ対策


🍀無料でカウンセリングします🍀
まずはお気軽にお問い合わせください。

