厚生年金保険制度改正の概要
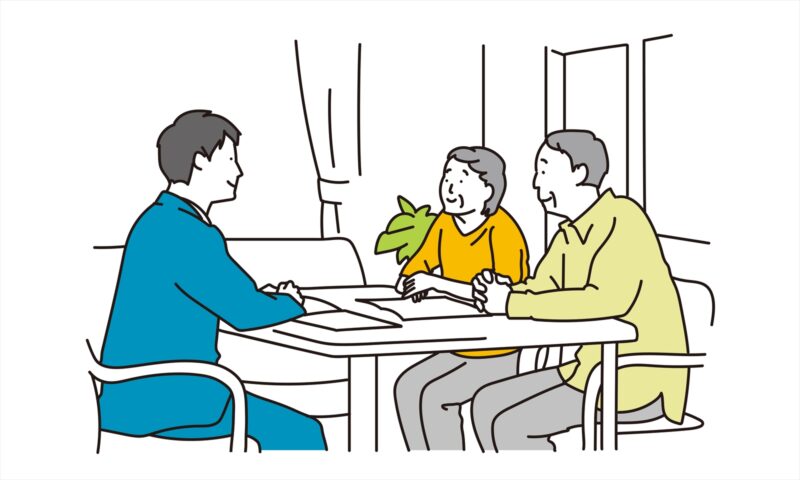
厚生労働省は6月30日に、厚生年金保険料の計算ベースとなる標準報酬月額の上限を、現行の65万円から75万円まで段階的に引き上げると発表しました。上限額の引き上げは今年から4年かけて行われ、そのスケジュールは次の通りです。
- 2027年:68万円
- 2028年:71万円
- 2029年:75万円
ちなみに労働保険料は事業所単位で1年間の賃金総額に料率を乗じて保険料を一括で計算しますが、社会保険料の場合は被保険者の月々の報酬ごとに計算するため、個々の報酬額を標準報酬月額にあてはめて、簡便に保険料を計算する仕組みになっています。
令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表_北海道(協会けんぽ)
保険料アップは高額所得者の救済か?

従来、厚生年金保険法では、標準報酬月額の最高額が被保険者の平均標準報酬月額の2倍を超えた場合に限り、最高額をもう1ランクアップする仕組みでした。しかし今回の改正は、このルールとは別に4年間で3ランクもの大幅な引き上げを実行するものです。
厚労省によると、月収65万円以上の高額所得者は、将来の老齢年金を増やしたくても標準報酬月額の上限(65万円)に阻まれて”損をしている”ので、今回の改正で救済するとのことです。もっとも日本の公的年金は「世代間扶養方式(後述)」であることに要注意です。
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げについて(厚生労働省)
年金財政均衡と所得格差のジレンマ

健康保険料の標準報酬月額上限は139万円で、厚生年金保険の2倍以上の幅に設定されています。これは日本の保険診療が公定価格であり、保険料の納付額に関係なく全員が同じ医療サービスを受けられるため、応能負担の原則により幅広く保険料を徴収しているためです。
一方、厚生年金保険では被保険者期間中の標準報酬月額の平均値で老齢年金額を計算するため、所得格差が年金格差に直結します。社会保険制度として老後生活の所得格差を助長することは好ましくないという考えから、これまで標準報酬月額の幅を抑制してきました。
しかし今回の改正以外にも、2029年までに任意加入だった5人未満の個人事業者が強制加入となったり、10年以内に全事業所において短時間労働者の厚生年金保険加入が義務化されるなど、保険料収入を確保するためには、多少の格差はやむなしといった感があります。
賃上げしたから保険料アップ!?

厚労省の説明では「賃金」という表現が多用されています。ただし「賃金」は労働者のみが加入する雇用保険料や労災保険料の計算に使用される用語です。経営者も加入する社会保険では「報酬」という表現が正解ですが、「賃上げ」と結びつけたい思惑が透けて見えます。
資料では「賃上げが進んだので標準報酬月額の上限も引き上げます」と説明しています。ところで「毎月勤労統計」によると、サラリーマンの賃上げ率はこの10年間で8.7%です。同期間の消費者物価指数が14.8%もアップしているのに比べると、賃上げが進んだかは疑問です。
しかもこのデータは大企業を含めた数値です。中小企業庁は中小企業の上げ率を4.0%と発表しています。また中小企業において標準報酬月額65万円以上の高給取りの労働者がどれほどいるのか疑問です。よって改正の影響を最も強く受けるのは中小企業の経営者といえます。
保険料アップ=年金アップではない

厚労省資料の「賃金に対する保険料の割合」では、被保険者負担分の9.15%しか表記されていませんが、本来の厚生年金保険料率は18.3%で、これを事業主と被保険者が折半します。事業主であり被保険者でもある中小経営者は18.3%をそっくり負担することになります。
標準報酬月額が65万円から75万円に上昇した場合、中小事業者本人分の厚生年金保険料は、年間で22万円の増加となります。その分、将来の老齢年金の支給が増えるか、といえば話はそう単純ではありません。それは日本の公的年金は「世代間扶養方式」だからです。
世代間扶養方式とは、現在の高齢者の老齢年金を、現役世代の保険料で賄う仕組みです。標準報酬月額の上限が引き上げられたからといって、増加した保険料が自分の年金となって還ってくる訳ではありません。自分の年金はその時の現役世代と高齢者の割合次第です。
年金財政の問題は会計制度の見直しから

少子高齢化に歯止めがかからない今の日本において社会保険料の引き上げと老齢年金の減額は仕方ないと思います。ただ今回の改正で全額を社会保障費に充当するはずだった消費税増税分の財政効果についてなんら具体的な説明がなされないのはとても疑問です。
例えば人事コンサルティングでは人件費の多寡を売上高や粗利益高との対比で検証します。年金財政においてもまず収入と支出のバランスから議論すべきですが、一般会計や特別会計といったお役所特有の複雑怪奇で不透明な会計ルールが問題をややこしくしています。
世間では為政者にはびこる利権と税金の中抜きがなにかと話題になっています。それらの真偽は筆者の関知するところではありませんが、年金財政の再建には、民間企業に準じた複式簿記と会計規則に改め、予算実績コントロールを行うことがマストではないでしょうか。

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。


🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。